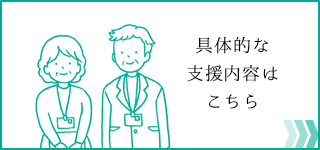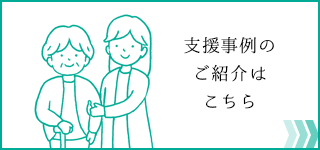法定後見開始までの流れと
報酬の目安
法定後見開始までの流れ
個別相談
- 相談者から、ご本人の生活状況や健康状態をお聞きします。
- ご本人にとって、法定後見制度の利用が適切かを話し合います。
後見等の
申立
- 後見制度の利用が必要と判断された場合は申立ての準備に入ります。
- 申立人は、ご本人またはご親族(4親等以内)、市町村長となります。
- 家庭裁判所への申立書類は、所定の書式となります。
- やすらぎが、無償で申立てのお手伝いをすることも可能です。
裁判所の
審議
- 家庭裁判所が、申立て書に基づき審議を行います。
- 裁判所は、必要に応じてご本人に面談したり、ご本人の精神鑑定を行うことがあります。
裁判所の
開始審判
- 家庭裁判所の審議を経て、ご本人の後見等の開始と選任された後見人名等を記載した
審判書謄本が届きます。
法定後見
の開始
- 法務局に後見等の開始と選任された後見人等が登記されます。
- 後見人等による支援業務が開始されます。
法定後見開始後の具体的な支援内容に
ついては
こちらを御覧ください。
法定後見の報酬の目安
成年後見人等が行う後見事務に対する報酬額は、家庭裁判所が対象期間の事務内容や
被後見人の財産状況などを総合的に判断して、妥当な金額を裁定(審判)します。
成年後見人等は、被後見人の財産の中から、
家庭裁判所の審判により示された報酬額を受け取ることが出来ます。
成年後見人等の基本報酬額の目安
(横浜家庭裁判所)
| 条件 | 月額報酬(内税) | |
|---|---|---|
| 管理財産 | 1千万円以下 | 2万円 |
| 1~5千万円 | 3〜4万円 | |
| 5千万円以上 | 5〜6万円 |
*身上監護や財産管理において特別な業務が発生した場合には、基本報酬額の50%の範囲内で相当額の付加報酬が付与されます。
やすらぎでは、生活保護受給者の方など、経済的に恵まれない方の後見支援も行っています。
また、各市町村では後見報酬の支払いを支援する「成年後見制度 利用支援事業」を
実施していますので、各行政機関が定める利用対象要件に該当すれば
後見報酬の助成を受けることが出来ます。